声に悩む必要はありません
英語でプレゼンするとき、「声が小さいから伝わらないのでは」「通らない声だと思われるのでは」と不安になる人は多いものです。特に日本人は控えめな話し方をする文化があるため、英語で堂々と話すことに抵抗を感じやすいといわれています。
けれども安心してください。声質や声量そのものを心配する必要はありません。 プレゼンで大切なのは、声を大きくすることではなく、「自分のペースをつくり、コントロールすること」です。声は、発音・抑揚・間の工夫によって、驚くほど伝わりやすく変わります。

1. 発音をクリアにする ― Stress / Rhythm / Linking
まず意識したいのは「声を大きくする」のではなく「声をクリアにする」ことです。ここで役立つのが、英語の3つの基礎:
- Stress(ストレス):大事な単語にだけ力をのせること。
- Rhythm(リズム):強弱の波を意識すること。
- Linking(リンキング):単語同士を自然につなげて流れを作ること。
例文:
This solution will make a difference
大事な単語にストレスを置くだけで、声が小さくても堂々と聞こえます。
2. 抑揚と強調をつける
単調に話すと、どんな声でも弱く聞こえてしまいます。逆に、重要な単語に抑揚をつけると、聴衆の記憶に残ります。
練習法はシンプル。原稿に下線を引いて、そこだけ声を少し強めること。
例:
Our team achieved an important result
こうするだけで、内容に力が宿り、声が聴衆を惹きつけます。
3. 間とリズムで堂々と見せる
声の大きさ以上に効果的なのが「間」です。1文ごとに1拍置くだけで、落ち着いて見え、聴衆は「堂々としている」と感じます。TEDのスピーカーや著名なプレゼンターも必ず間を活用しています。
実は国際会議でも、日本人スピーカーの落ち着いたテンポが“聞きやすい”と評価されることがあります。語彙や文法がシンプルで、スピードがゆったりしているからこそ、多国籍の聴衆に伝わりやすいのです。これは「声が小さいから不利」という発想とは真逆で、むしろ自分のペースを活かした強みといえます。
実際、国際学会では日本人研究者の発表が「わかりやすい」と評価されることが少なくありません。語彙や文法はシンプルでも、落ち着いたリズムでゆっくり話すことで、英語を母語としない聴衆にとって理解しやすいのです。同じように、留学生のプレゼンでも「派手さはないが、聞き取りやすい」と好印象を持たれる例があります。これはまさに、声量ではなく自分のペースをコントロールする力が強みになっている証拠です。

まとめ ― 自分の声を活かす
プレゼンは「声質や声量」で決まるのではありません。
大切なのは:
- 自分のペースを掴み
- それをコントロールし
- 表現力をつける
その延長に、自分の声の特徴を最大限活かすという答えが見えてきます。
- Stress / Rhythm / Linking で声をクリアに
- 抑揚と強調で内容に力をのせ
- 間とリズムで堂々と見せる
これらを積み重ねれば、声は自然と「伝わる声」に変わります。
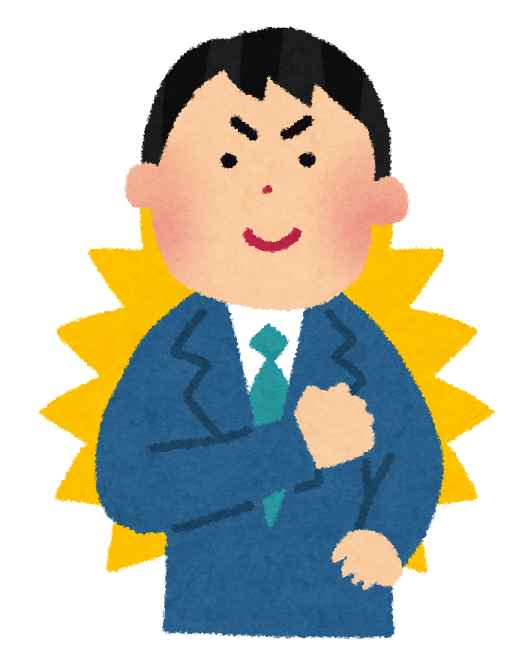
どうか「自分の声は弱い」と悩まないでください。あなた自身の声を最大限に活かす工夫こそが、聴衆に届く力になります。
次回は、声と並ぶもうひとつの柱――表情についてご紹介します。

コメント